今私が一番関心を持っていること。それは「ヴィーガニズム」だ。
去年秋頃からヴィーガニズムについて強く意識するようになり、2023年年明けと同時にヴィーガンになると決意した。
まずは食生活。現在家の中にストックしてある動物性の食品や調味料は無駄にせず使い切ることにはしているが、外食を含め食事の面で、肉・魚・乳製品・卵を新しく買うこと、口にすることはやめた。そして食だけでなく衣食住でいうならば「衣」「住」においても動物搾取を取り除く選択をしている。
この記事では、私がヴィーガニズムについて知ることになった経緯、なぜヴィーガンになろうと思ったのか、シェアしたい。ヴィーガンとは完全菜食主義者のことでもダイエット法でもない。食だけに焦点を当てるとヴィーガンの食事は完全プラントベースとなる。けれどヴィーガニズムとは食に限らずいかなる場合でも可能な限り動物搾取をしない生き方のこと。
ヴィーガンになるということは今後のライフスタイルが大きく変わる。当時の気持ちをいつまでも忘れないためにも、ヴィーガンになると決めた時の心境をここに書き留めておこうと思う。
ヴィーガニズムって何?ヴィーガンになるということ
世界で最初のヴィーガン協会とされる英国ヴィーガン協会による「ヴィーガニズム」の定義を引用する。
“Veganism is a philosophy and way of living which seeks to exclude – as far as is possible and practicable – all forms of exploitation of, and cruelty to, animals for food, clothing or any other purpose.”
The Vegan Society
ヴィーガニズムとは、可能かつ実践的な限り、食用、衣料用、その他のあらゆる目的のために動物を搾取すること、動物に残虐な行為を行うことを排除しようとする生き方。
ヴィーガニズムに興味を持つきっかけは健康面への配慮、環境問題などあると思う。でもヴィーガニズムの根底にあるのはアニマルライツ。人間と同じように痛みや苦しみを感じる動物は、動物らしく生きられる権利、人間の都合のために危害を加えられない権利を持っていて、それらの権利は守られべき。きっと苦しみを感じる相手に暴力を振るったりあえて苦しみを与えようとする人は少ないはず。それは動物に対しても言えること。
私がヴィーガンになると決めた理由は人間による過剰で残虐な動物搾取の現実を知ったから。今まで知らずに生きてきたからこそ本当にショックだった。そして知ったからには動物たちの苦しみにこれ以上加担したくない、どんなに小さくても動物たちのため自分にできることをしようと決めた。
ヴィーガニズムを知ったきっかけ
1. インスタでの出会い
このブログでこれから私のヴィーガンジャーニーを書こうと決めた時、そもそもどのような経緯で私はヴィーガニズムについて知ったんだっけと思い返してみた。
そうだ。2年前、インスタで出会ったライターのCookieheadさんが手がけるウェブマガジン「The Little Whim」だ。
ヴィーガンであるCookieheadさんが書かれる文章はとにかく魅力的でいつも引き込まれるように読んでしまう。私なんかが言うのは大変おこがましいのだけど、どんなトピックでもその文面には誠実さと優しさが詰まっている気がするし、ヴィーガニズムに関して書かれている記事も熟読させていただきいつも学びを得ている。
私はこのウェブマガジンでクルエルティフリー(動物実験がされていない)プロダクトについて初めて知った。聞いたことはあったけどあまり考えたことはなかったワードが、途端に意味を持つリアリティに変わったのを今でも覚えている。私たちが日常で使っている多くのものが罪のない動物たちへの実験を経て商品化されているなんて衝撃だった。そしてその実験のためだけに繁殖され、一度も陽の光を見ることなく亡くなっていく動物たちがいる。
以前からパッケージの裏の表記をよく見る習慣があったけれど、以来、商品がクルエルティフリーであることを表すウサギのマークも意識的に探すようになった。
今まで慣れ親しんできた習慣から離れ新しいライフスタイルを築いていくのは想像以上に困難なことだと思う。でもそれが意識的にはっきりしていることならまだしも、産まれた時から当たり前のことだったらどうだろう。疑問を抱くことさえない、巧みに日常生活に組み込まれていることだったらどうだろう。
おそらく私と同年代で生まれた時からヴィーガンの人はそんなにいないんじゃないかな。今ヴィーガンとして生きている大人たちは、みんなどこかで得た何かのきっかけからヴィーガンになったのだと思う。
私は、Cookieheadさんのブログを読んでからヴィーガンになろうと決意し実際に行動に移すまでおよそ2年かかった。その間常にヴィーガニズムについて意識していたわけではないし、知った後もすぐに行動に移せなかったり、日常に戻ったら忘れてしまうこともあった。
しかし、去年秋頃からあるきっかけによりヴィーガニズムについて強く意識するようになった。ヴィーガニズムについてソーシャルメディアで発信している人たちをフォローし始め、目を背けず真実と向き合う度強く衝撃を受けながらも、知りたい、知らなくては、と貪るように過去の投稿を見ていた。
ヴィーガンになるまで2年という月日は流れたが、最初の大きなきっかけを作ってくれたCookieheadさんには本当に感謝している。そして今、点と点が繋がり、私の中にあの時蒔かれた小さな種がついに芽生えた。そんな感覚でいる。
2. 愛犬の存在
私がヴィーガニズムに強く意識するようになった理由。それは愛犬の存在から始まる。
ニューヨークでは街中で保護犬の譲渡会を頻繁に見かける。保護された犬たちと里親となる人たちとを繋ぐイベントだ。私たちが愛犬をいつも散歩に連れて行く公園の直ぐそばでも毎週末のように行われていて、大変賑わっている。ニューヨークに住んだことがなければこんなにも動物保護活動が身近に感じられなかったかもしれない。
我が家には5歳になる犬がいる。ブリーダーから直接迎え入れた子で、大切な大切な家族の一員。しかし日本で犬を家族に迎えようと思った際、保護犬という選択肢は浮かんでもこなかった。大変残念だけどそれが事実だ。
動物を「買う」という行為
ニューヨーク州ではほんの一ヶ月前、嬉しいニュースがあった。
犬・猫・ウサギをペットショップで販売をすることを禁止する「パピーミルパイプライン」法案が、キャシー・ホークル州知事の承認により、2024年からついに施行されることが決まった。
ありがたいことにパピーミル問題について日本語でも英語でも情報をシェアしてくれている方たちが沢山いる。
可愛い動物を「買う」という行為の裏には、営利目的のため劣悪な環境の元繁殖を繰り返させられる親犬や親猫たちがいて、このようなかたちで生まれた動物たちは商品として生体販売を行うペットショップなどに転売される。
今回成立した法により、今後ニューヨーク州でのパピーミルパイプラインは閉鎖され、ペットを家族に迎えたい場合、ペットショップではなく保護施設から保護動物をアドプトすることがメインストリームになっていくはず。これにより少しでも殺処分となる動物が減ることに繋がるのであれば嬉しい限りだ。
我が家の愛犬はブリーダーから迎え入れたけれど、実際に生体販売を行うペットショップにも足を運んだし、動物の命を買ったという行為には変わらない。我が子を産んでくれ、その兄弟姉妹たちを産み、それを何度繰り返したかは分からない、繁殖のために命を削っている親犬がいるという事実も変わらない。こういった背景について当時考えもしなかった自分自身に腹が立ったし、罪悪感を感じた。愛犬に対する愛情は今もこれからももちろん変わらない。でも知ったからには事実から目を背けず、これからできることをやっていきたいと強く思った。
3. Speciesism(種差別)
それから犬を助けたい、保護犬たちのために何かしたいと思い始めたのはごく自然な流れだった。2022年秋頃、犬食文化のあるアジアの国から食肉として犠牲になろうとしている犬たちをレスキューしている保護犬団体でボランティアをすることが決まったのだが、保護犬ボランティアに関しソーシャルメディアやネットでリサーチしていた時、「種差別」という言葉と出会った。
犬や猫と家畜と呼ばれる動物たちの違いって一体何?この問いを突きつけられ物凄いショックだった。言うまでもなく犬や猫の保護活動は意義のあることだけど、その裏で毎年億単位で家畜と呼ばれる動物たちが命を失っている…
動物だからって人間の命の重さと変わらないはずだし、それは動物間でも同じはず。なぜ犬は愛されるべき存在で、パピーミル廃止のため法律が可決される一方で、人間のために毎日犠牲になっている動物たちがいるんだろうか。その違いって一体何?そしてこれは人間対動物の域を超え、人種差別や性差別など、属性により抑圧を受け差別の対象となるという人間社会での問題とも繋がっている。
この矛盾に気づいた時の衝撃は今でも忘れないし、犬を飼っている立場としては尚更のことだった。
子供の頃から当たり前のように肉や魚、卵が食卓に並び、今まで何の疑問も持つことなく食べてきた。牛乳を飲まないと背が伸びないと教えられたし、タンパク質=赤身のお肉だと思っていた。「習慣」、「カルチャー」、「常識」、「今までそうしてきたから」を前に「なぜ?」と問いかける人はどれだけいるのだろう。
そしてその「なぜ?」の後に生まれるモヤモヤや違和感、罪悪感やイライラといった感情。認知的不協和だ。動物を虐待することは間違っていると理解しているのに、日々動物を利用し食べているという行動には大きな矛盾が存在する。なんだか厄介なことを知ってしまったと思うかもしれない、当たり前だと思っていた裏にある真実があまりにも残酷過ぎて目を背けてしまうこともあるだろう。私もそうだった。
ここでシェアした動画で講義を行っているのはEartling Edことイギリスのヴィーガン活動家であるEd Winters氏。YouTubeではこの講義の全編を見ることができる(動物の映像は含まれない)。この講義の中で彼が言った言葉が忘れられない。「Are our taste buds more important than the life of an animal?」動物たちの命と美味しいからという理由で彼ら彼女らを犠牲にすること、どちらが重要なのだろうと問いかけている。
2年前コップに注がれた一滴の水から始まり、小さな選択を繰り返し、保護犬活動をきっかけに種差別について知り、倫理観と実際の行動のギャップからくる認知的不協和と向き合った私は、なんでもっと早く気づかなかったんだろうと罪悪感でいっぱいになった。
ここから私のヴィーガニズムへの意識は一気に加速する。
ヴィーガンになる決心がついた
前述でシェアさせていただいた投稿の主であるStill a Veganさん自身がヴィーガンになったきっかけとしてインスタでシェアされていた「世界で一番重要なスピーチ」。
何となくこれを見るのをしばらく避けていた気がするけど、2022年の年末、ついに私もこの動画を見て気持ちが固まった。
行動を起こさない、という選択肢がもう私の中に残っていなかったことは自覚していたのに、これを見てしまったら最後、もう後戻りできないことも分かっていた。ヴィーガンになるということは今後の生き方が変わるということ。どこかで最後の足掻きをしていたのかもしれない。
私はヴィーガンになると決めた、とパートナーに打ち明けたらなんだかとっても気持ちが楽になった。既にプラントベースの食事を取り入れ始めていたし、薄々私の気持ちにも気づいていたんだろう。ありがたいことに好意的に受け止めてくれ、サポートすると言ってくれた。
ヴィーガンになったことでモヤモヤが消えた。知らなかったとはいえ誰かの苦しみに長い間加担してきた事実は残念ながらなくならない。罪悪感を感じる理由と向き合うことは胸が締め付けられるほど辛いプロセスだったけど、今は自分の気持ちに正直に生きられるようになった。ヴィーガニズムは私のアイデンティティだ。
ヴィーガンというライフスタイルを選択したからには
苦しい、ではなく楽しむこと
ヴィーガンになると決心するまでの過程で、目を背けずにはいられない胸が苦しくなる映像を何度も見た。あまりにもショックで眠れない夜もあった。正直今でもその苦しみはなくなっていないし、これからも消えないと思う。
かわいそう、辛い、という感情はもちろんアクションを起こす原動力となるけれど、ネガティブになりすぎて胸が押し潰されそうになる時もある。
保護犬のボランティアをしようと決めたと友人に話した時。かわいそう、やるせない、そんな気持ちが先行していた私に、彼女は「ボランティアをやることで貢献できることは?ポジティブな変化に目を向けてみて。せっかくやるのなら楽しみながらやらなくちゃ」、と言ってくれた。確かにそうだよね。苦しいと思いながら行動するよりも、小さな成功体験を積み重ねながらその変化を楽しんだ方が絶対いいに決まってる。
ヴィーガニズムについて知れば知るほど、動物だけでなく、あらゆる環境・社会問題と密接に結びついていることにも気づく。問題のあまりの大きさに正直途方に暮れることもあるし、ちっぽけな私が変わったところでと思うこともある。
それでも変わらずにはいられない。
私たちが生きている社会から動物たちの苦しみを完全に取り除くことは残念ながらできない。でも完璧を求めるのではなく、できることから少しづつでも変えていくことにフォーカスして、ヴィーガンライフをエンジョイしようと思う。今は新しいレシピや食材を試したりするのがとても楽しいし、これからニューヨークに沢山あるヴィーガンレストランやカフェを開拓していくことにワクワクしている。
思いやりの心:実はとってもシンプルなことかもしれない
毎晩、娘が寝る前にベッドで一緒に絵本を読んでいる。娘がお気に入りの絵本の多くには動物たちがキャラクターとして描かれていて、見ているだけでほんわか優しい気持ちにさせてくれる。そして毎晩必ず一緒に寝ているぬいぐるみたちには、おさるさんやうさぎさん、クジラさんにぞうさんがいる。彼女はそのぬいぐるみたちをお友達と呼び、一人ひとりには違った個性があるそうで、それぞれに対し彼女なりの思い入れがある。
結局行き着く所は絵本の中で描かれる動物たちが教えてくれる優しさや思いやりの心なんじゃないかと思う。絵本のキャラクターやぬいぐるたちは、現実世界で声を上げることのできない動物たちの代弁者なんじゃないか、最近そんな気がしてならない。誰に対しても、それが人間であろうが動物であろうが、お互いに思いやりを持って接することができたらいいな。
編集後記
この記事を書くことは私にとってとても勇気のいることでした。反対意見もあるだろうし、人によって受け取り方も違ってくると思います。公開するまでに何度も書き直し、数ヶ月後読み返した際、あまりにも読みにくさが際立っていたため加筆修正しました。自身の記録とはいえ、シェアするからには一人でも多くの人に知ってもらいたいという気持ちももちろんありました。込み上げてくる思いがあり投稿するかどうか迷いもありましたが、結局今の自分には経験をありのままに書くことしかできません。どんな感情だろうと何か感じてくださったらそれだけでとても嬉しいです。長くなりましたが最後まで読んでくださりありがとうございます。
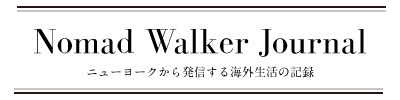





コメント