ニューヨークで大人が子供と接している様子を見て、娘との関わり方で参考にしたいなと思うことがいくつかあります。その一つは子供の褒め方。親たちは子供と積極的に会話をして、子供のことをとにかくよく褒めているように見えます。
最近よく聞く子供の「自己肯定感」を育てる教育方法。どうやら褒めることが大事なようで、それもただ褒めるだけではなくその褒め方に鍵があるようです。
自己肯定感に関する育児本を何冊か私自身目を通したことがあるので、褒めることが大事なのは理解しつつも、余裕がなかったりすると、つい癖ですぐに「ダメ!」や「やめなさい」と言ってしまったり、「すごいね」「上手だね」という抽象的な言葉をかけてしまいます。
一方で、周りの親たちは子供のことをよく観察し、ポジティブかつ具体的な褒め方ができている印象があります。
もちろん皆パーフェクトではなく試行錯誤してるんだとは思いますが、個々を重んじるアメリカだからこそ、子供も大人と対等の立場にある一個人として接することが自然と身についているのかもしれません。特に多様性に富むニューヨークにいると、皆違って当たり前。個性を活かす生き方が大切な気がします。
では、私がニューヨークで目撃した親と子供との接し方で、私も参考にしたい・真似したいなというポイントを具体例と共にいくつか紹介してみようと思います。
褒め方がスマート
ある朝いつもの公園で仲良しの友達と娘がキックボードに乗って遊んでた時のこと。友達の乗るキックボード進行方向に娘たちより少し月齢の低い子供がヨチヨチと歩いて来ました。
思わず「危ない!」と私は叫んでしまいましたが、その友達は衝突する前に無事停止しました。

するとその子のママは、
「That was a good stop! You used your eyes and ears really well! I’m so proud of you!」
「あなたはちゃんと自分の目と耳を使って危険を察知し上手に止まることができた!すごいじゃない!」
と言い、「人にぶつかる前にちゃんと止まることができた」ということを最大限に褒めたのです。そして、止まれたとはいえびっくりして動揺している様子の我が子を落ち着かせるため、抱きしめながら何度も優しく繰り返し言い聞かせていました。
そしてヨチヨチ歩きの子の親も一緒になって「よく止まれたね!」とその子を褒めていて、私はなるほどなーと感心してしまいました。
恐らく私が同じ立場だったら、「止まれた」という事実より「あともう少しでぶつかって小さい子を怪我させてしまったかもしれない」という点から娘に注意をしていたと思います。
子育てをしているとどうしても、「できない」「言うこと聞かない」と親の思い通りにならないマイナス面に目がいってしまったりします。また、相手の親との関わりものあるので、きちんと叱ったり言い聞かせているところをちゃんと見せなければと、ついつい我が子の行動を褒めることよりも注意することを優先してしまうこともあります。
これはちょっと極端な例ではありますが、娘のお友達はちゃんと止まって危険を回避できた。「危なかった」ということではなく、まずは子供のできたこと、やれたことをちゃんと認めて褒めてあげる。シンプルなのに意外とできていなかったことにハッと気付かされました。
「ありがとう」を積極的に言う
ニューヨークで親と子供との接し方を見ていてよく耳にするキーワードがあります。それは「Thank you」です。これも一見当たり前なことですが、ついつい言い忘れていたワードでした。
何かできた時、「Good job」(よくできたね)と言う前に、まずは「ありがとう」と言う。例えばお友達に自分のおもちゃを貸してあげられた時、おやつを半分こできた時など、まるで相手の子の代弁をするように、我が子に向かって「〇〇ちゃん、ーしてくれてありがとう」と言います。
大人同士であれば相手が何かしてくれた時自然とありがとうと言えるのに、ついつい子供が相手だとこの言葉を忘れてしまいがちです。子供も意思を持った立派な一人の人間。こうしなさい、ああしなさいと言い大人の思い通りにできたからすごいね、ではなく、やってくれてありがとう、と言う気持ちを周りの目を気にせず自然に伝えられる現地ママたちはすごく素敵だなと思います。

娘は1歳半ごろからよく大人の真似をして家のことを手伝うようになりました。おそらくこのくらいの年齢だと皆同じだと思いますが、自分で何もかもやりたいと行動してはよく失敗し、泣いたり癇癪を起こします。
- スーパーの買い物袋から中身を取り出しキッチンに運んでいる途中落とす、泣く
- 犬のお水を取り替えようと容器を持ち上げて水をこぼす、こぼれた水で遊び始める
- 洗濯物をかごから取り出し畳もうとするがうまくできず、癇癪を起こしてかごの中身を全てぶちまける
などなど。
以前は、お水またこぼした、あー卵割れちゃったーと、結果にフォーカスしイライラしていました。でも今はひとまず親の都合は置いといて、まずはお手伝いしてくれてありがとう!と伝えるようにしています。すると彼女はとても嬉しそうに満足気な笑顔を見せてくれ、どんどん積極的にお手伝いをしてくれるようになりました。
大人が一人でやるよりも時間もかかれば仕事も増えてしまいますが、娘のやりたいという気持ちを尊重し、お手伝いに限らずありがとうの気持ちをちゃんとこれからも伝えていきたいと思います。
周りの大人に対して
そして人から自分の子供を褒められた時。日本にいた時はどうしても謙遜してしまい、そんなことないよーとデフォルトで答えてしまうことがよくありました。否定とまでいかなくても、自慢しているように聞こえないよう当たり障りのない反応をすることも多かったです。
でもせっかく褒められたのに、子供の前で親がそんなことないって言ったらきっとその子は傷ついてしまいます。
アメリカでは、褒められたらシンプルにまず「Thank you」、そして大抵、「そうなのよ、この子はね…」と話が広がります。
周りにどう思われるかより、我が子がどう感じるか、その子の気持ちをまずは一番に考えてあげるべきだと改めて気付かされました。
娘を見ていても思いますが、子供って本当に大人の動作を細かく観察しています。大人同士の何気ない会話ややり取りの中からも、その場の空気を誰よりも敏感に感じ取っています。
この子はまだ小さいからと子供扱いせず、子供の気持ちを尊重した振る舞いを心がけ、何よりも子供にとって一番の味方でありたいなと思いました。
テイラースイフトに見る「いい子」症候群
Netflixで配信されているテイラースイフトのドキュメンタリー映画「Miss Americana」。日本でも人気な彼女なので、見た方も多いかもしれません。
世界的スターの彼女が内なる葛藤を経て、夢をカネえる姿を描いた内容なのですが、この映画の中で最も興味深かったのは、彼女の「Good girl(いい子)」であり続けるための苦悩。
彼女が「Those pats on the head were all I lived for」と言うように、小さい頃から頭を撫でてもらうこと、つまり「あなたはいい子ね、偉いわね」→ 「優秀なシンガーソングライターね」と周りから評価してもらうことを求め続けていたそう。あれほどの名声を得た後も優等生で在り続けるため型にはめられ、周りからの期待に応えるため「正しい」振る舞いをし、「I’ve been trianed to be happy when you get a lot of praise」と、周りから賞賛を得ることこそが自分の幸せだと思っていたそう。
このドキュメンタリーを見て思い出したのが「praise junkie」という言葉。
この記事によると、Praise junkieとは「Good job / すごいね、よくできたね」というジャッジをしたり大人が価値を決めてしまう(good jobかgood jobじゃないか)褒め方を続けてしまうと、褒められることや認められることに依存してしまい、大人になってからも自分の価値を周りの評価で測ってしまう可能性があるそう。
その他にも失敗を恐れてリスクを取らなくなる・チャレンジしなくなる、人の顔色を伺ったり評価を気にして自分の意見に自信が持てなくなるなどの影響があるのだそう。
テイラースウィフトがpraise junkieになったのは、恐らく小さい頃から厳しいエンターテイメントの世界で仕事をしてきて、常に周りからの批判、評価にさらされてきた影響が大きいのかなと思います。彼女の葛藤をなんだか親目線で見てしまい、胸が少し苦しくなりました。
では子供がpraise junkieにならないようにするにはどうしたらいいのか。
ネットなどでこれに関してはたくさんの情報を得ることができますが、推奨されている方法のいくつか例をあげると:
- 子供の行動を観察して事実をそのまま伝える(例えば、絵を見せられたら「青をたくさん使ったんだね」「丸をいっぱい描いたんだね」、おやつをお友達とシェアできたら「お友達は〇〇ちゃんからお菓子を分けてもらえて嬉しそうな顔してるね」など)
- 結果ではなく、その過程や前回と比べて上達したことを褒める。できたことに「すごいね」、できなかったことに「残念」だと「できる」こと=価値があり、できないかもしれないと思うとチャレンジすることが怖くなってしまうので、過程を褒めることで結果ではなくチャレンジすることに価値があるということを教える
前述のアメリカ人ママの例では「ぶつかる前に止まった=できたこと」に対して褒めているので、究極論、ここでいう推奨されている方法ではないかもしれません。
ですが恐らくここで注記しなければいけないのは、「good job」と言ってはいけない、結果を全く褒めてはいけない、ということではないと思います。
特に子供が小さい頃は、初めてつかまり立ちをした瞬間、初めて歩いた時、など「初めて」の経験がたくさんあるし、親が「すごいね!!」といって一緒に喜びを共有することはとても大切じゃないかと思います。実際そんな嬉しい瞬間に立ち会うことができたなら、自然と感動してそういう言葉が出てきますしね!
大きくなるにつれ周りのこともよく分かるようになってきてからは、過剰に「good job」を言うのを控え、他の言い方に変えてみる心がけをすればいいんじゃないかな、と私なりに解釈しています。
正解のない子育て
子育てって本当に難しいです。
子供を褒めてあげることはとてもいいこと。でも過剰に褒めすぎるのは逆効果になるし、褒め方に注意しないとチャレンジ精神に欠ける自信のない子に育つかもしれない。
やっぱり娘には自分に自信を持って欲しいし、周りの目を気にせず堂々と自分の意見を言える大人になって欲しいと思います。でも同時に子供も一人の意思を持った人間で、一人一人個性が違う。一般的に「これが正しい」と言われている方法だとしても、それがみんなに当てはまるとは限りません。
ニューヨークで見た親たちのポジティブな褒め方をお手本にしつつ、「こうするべき」という方法に縛られ過ぎずやっていけたらいいなと思います。
これからもずっと試行錯誤は続きそうです。
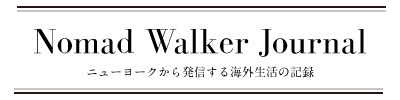


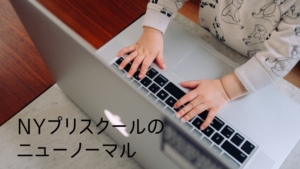



コメント